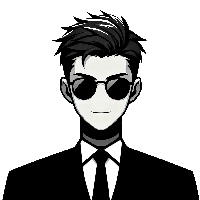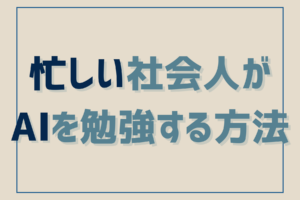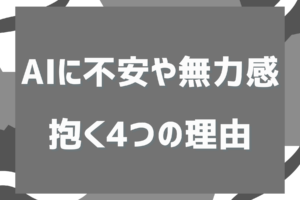最近AIを勉強する方が増えてきています。
そのなかであなたも「自分もAIを勉強したい」と思っているのではないでしょうか?。
そして「AIの勉強は何から始めたらいい?」という疑問もあるのではないでしょうか?
本記事ではその疑問を解決するため、AIの勉強を何から始めるべきか丁寧に解説しています。
この記事を最後まで読み実践すれば、AIの勉強を始める準備が整います。ぜひ最後までお読みください。
・AIの勉強は何から始めたらいいか分かる。
AIの勉強は何から始めるといい?
AIの勉強は何から始めるといいのでしょうか?
Pythonを勉強するといい、というのをよく見聞きします。これは間違ってはいないのですが、Pythonを勉強する前にするべきことがあります。
AIの勉強を始める際に最初にやることは、Pythonの勉強ではなく、「目標を明確にする」ことです。その次に「必要な知識を把握」して「学習方法」を決めます。最後に「環境を整え」て、ここで初めてPythonの学習を始められます。
AIを勉強する目標を明確にする
AIを勉強する際、最初にやることは何のために学ぶのか、「目標を明確」にすることです。なぜ、目標を明確にすることが重要なのでしょうか。それには次の2つの理由があります。
- 学習効率が上がる
- モチベーションを維持できる
目標を明確にすることで、必要な学習範囲を絞り込むことができるため、無駄な勉強を避けられます。その結果学習効率が上がります。
たとえば、「AIを使って仕事を効率化したい」という目標がある場合、必要となる知識はPythonの基礎やExcel連携、AIツールの使い方など、限定的な範囲に絞ることができます。
一方で、「AIエンジニアとしてキャリアを築きたい」という目的を持つ人は、数学(線形代数や微分積分)、プログラミング(Python、C++など)、さらには機械学習やディープラーニング、クラウドサービスの知識など、より幅広く深い学習が必要になります。
AIの勉強は一朝一夕で終わるものではありません。学習していくうちに「なぜ自分はAIを学んでいるんだろうか?」「AIを学んで意味があるのか?」といった疑問が思い浮かぶ瞬間が必ずあります。
このような疑問は厄介なもので、放置しておくとどんどん膨れ上がって、やがてモチベーションの低下を引き起こします。最悪の場合、挫折して勉強をやめてしまうことも考えられます。
目標が明確であれば、目標を思い出すことで疑問を解消し、モチベーションを維持できます。
たとえば、「AIを活用して副業をしたい」「AIエンジニアとしてキャリアを築きたい」「将来AIを活用して自分のビジネスを立ち上げたい」という明確な目標があれば、高いモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
目標を明確にする方法
目標を明確にするには、「自問自答」を繰り返すか、頼れる人に「相談する」かの2つです。この頼れる人というのは、AIに関する豊富な知識を持った現役エンジニアのことです。
そして、私のおすすめは頼れる人に「相談する」です。
なぜなら「自問自答」だけではどうしても限界があるからです。自問自答では自分の知識の範囲内で考えるので、自分の知らないことは目標にできません。そのため、「なかなか目標が明確にならない」といった問題が起きます。
ほかにも、あなたがやりたいことはAIでなくても実現できる場合がありえます。自分の知識の範囲内だけで考えると、こういったことに気づけず、時間を無駄にしてしまうかもしれません。
「自問自答」が無駄と言っているわけではありません。自分の興味や方向性をある程度考えたうえで相談すると、より具体的なアドバイスをもらいやすくなります。なので、相談する場合でも「自問自答」は重要です。
また、相談した結果をもとにもう一度「自問自答」を繰り返すことで、自分の考えを深め最終的に納得のいく目標を設定できるでしょう。
では、どこに「信頼できる相談相手」がいるのでしょうか?知り合いにAIに詳しい方がいるなら、その方に相談するのが良いでしょう。
しかし「AIに詳しい知り合いがいない…」という方のほうが多いでしょう。そもそもAIに詳しい人が少ないですからね。
でも安心してください。無料で信頼できる相手に相談ができる方法があります。
それは、プログラミングスクールの無料カウンセリングを受けることです。スクールでカウンセリングを受けることで、専門的なアドバイスやもらえます。
「無料カウンセリングを受けたら、スクールに入会しないといけないのでは…?」と不安に思う方もおられるかと思います。
今どき無理な勧誘をするスクールはあまりないですが、時代遅れで悪質なスクールがあることも事実です。
なので、安心して無料カウンセリングを受けられるスクールを3つ選びました。ここなら安心してしてカウンセリングを受けられ、無理な勧誘もありません。
必要な知識を把握する
目標が明確になったら、次は「目標達成に必要な知識を把握」しましょう。
事前に必要な知識を把握しておくことで、余分な学習をせずに済みます。他にも、学習計画が立てやすいメリットもあります。
例えば、AIの開発に使われるプログラミング言語はPythonが多いから、Pythonを学ぶ。機械学習やディープラーニングを理解するためには、線形代数や微分積分などの数学知識が必要だから、数学を学ぶなど。
必要となる知識はネットで検索する、あるいは書籍などから情報を集めると良いでしょう。そうすることで情報収集するスキルも身についてきます。
なにを学べばいいかわからない場合は、Pythonから学ぶと良いでしょう。PythonはAIの開発でよく使う言語なので、学んで損はありません。Pythonを勉強しつつ、ほかに必要な知識を調べれば、時間を無駄にせずに済みます。
もし、一人で考えるのが難しい方や、効率的に学習を進めたい方、忙しい方などは、プロのエンジニアに聞いてみるのも良いでしょう。
学習方法を決める
次に、「学習方法」を決めましょう。
この学習方法の選択を間違えると、学習効率が悪い、スキルが身につかない、といった状況に陥りかねません。なので、しっかり考えるようにしましょう。
とはいっても、学習方法は大きく分けて2つです。
「独学」か「人に教えてもらう」かです。
基本的には「人に教えてもらう」ほうが効率的にスキルが身につきますが、すでにプログラミングの経験がある方は独学でも大丈夫でしょう。むしろ自分のペースで勉強できるため、効率的になる可能性もあります。なので、まずは独学でやってみることをおすすめします。
逆に、プログラミング未経験や初心者が「独学」で勉強を進めていくのは難しいでしょう。初めて触れる知識が多いため、多くの壁にぶつかります。「独学」の場合、これら壁をすべて一人で乗り越えていかなければなりません。
それは非効率的なだけでなく、挫折する可能性も非常に高いでしょう。そのため、プログラミング未経験や初心者は「人に教えてもらう」=「メンター」の存在が必要不可欠といえます。
この「メンター」は、実務経験が豊富な現役エンジニアが好ましいです。現在のトレンドや必要とされるスキルの知見があり、実力がある可能性が高いからです。
このような「メンター」から教えてもらうには、スクールを活用するのがおすすめです。
環境を整える
最後に「環境」を整えます。
AIの勉強に必要なのは、開発環境とネット環境です。当記事を読んでいるということはネット環境は大丈夫でしょう。問題は開発環境です。
開発環境というのは、プログラムのコードを書いたり実行したりできる環境のことです。勉強する際も、この開発環境を整える必要があります。実際にコードを書いたり実行(=アウトプット)しないと、学んだことが身につかないからです。
開発環境は「実機のPC」か「クラウド」のどちらかです。
詳しくは↓の記事で解説していますが、かいつまんで説明します。

実機のPCの場合、PCの中にAIを開発する環境を整えます。機械学習やディープラーニング、分析などの開発を行いたい場合は、やや高額(18万円~25万円)なPCが必要になってきます。
クラウドの場合は、クラウド上にある環境を利用して開発していきます。有名なのは『Google Colab』で、無料で利用できます。
実務ではPCで開発を行っていくので、おすすめはPCの購入です。しかし高額なので、まずはクラウドで勉強を始めて、必要になったらPCを購入する流れが良いと思います。
スクールでAIを学ぶ場合は、クラウド上での学習が多いので、PCの購入は必要ありません。ただ、スクールによって異なるので、あらかじめ確認するようにしてください。
まとめ
AIの勉強をする際の手順をまとめると、以下のとおりです。
- AIを勉強する目標を明確にする
目標を明確にすることで、学習効率が上がるほかモチベーションの維持にも役立ちます。
- 必要な知識を把握する
目標から逆算して必要な知識をあらかじめ把握しておくことで、無駄な学習をせず効率的に知識を身につけられます。
- 学習方法を決める
自分に合った学習方法を選ぶことで、効率的にスキルを身につけられます。
- 環境を整える
AIを開発する環境を整えることで、AIの勉強を始められる状態にします
プロに相談するのが一番の近道
AIを勉強する目標を明確にする、必要な知識を把握する、環境を整えるといったことを説明してきましたが、未経験者や初心者にとっては難しいかもしれません。
やはりある程度の知識や、検索スキルが必要だからです。なので、難しいと思ったら一人で悩まず、プロに無料相談するのをおすすめします。
無料相談は、無料なので基本的にはメリットしかありません。しかしデメリットも多少あります。次で、無料相談をするメリット・デメリットをお伝えします。
無料相談をするメリット・デメリット
メリット
無料相談をするメリットは、以下が挙げられます。
- 目標を明確にできる。
プロの知見から、あなたの目標を明確にすることができます。業界について熟知している人と対話することで、本当に納得できる目標を設定しやすくなります。
- 必要な知識がわかる
あなたの目標を達成するために、どんな知識がどれくらい必要なのか分かります。自分の知識だけではわからない、本当に必要な知識をプロの知見から知ることができます。
- キャリアについて相談できる
AIを学んだあとのキャリアについて相談できます。AIを趣味で学ぶなら別ですが、仕事で使うなら学習後の方向性を決めることは重要です。
- スクールに入らなくていい
無料相談をしたからといって、スクールに入らないといけないわけではありません。無料相談をするだけ、といった使い方ができます。
デメリット
無料相談をするデメリットは、以下が挙げられます。
- オンライン
スクールの無料相談は、Zoomなどを利用してオンラインで行うことが多いです。オンラインでの面談や顔出しが苦手な方にとってはデメリットです。
- 相談後に勧誘される可能性がある
今どき無理な勧誘をするスクールは少ないのですが、まったくないとも言えません。勧誘を断るのが苦手な方にとってはデメリットです。
- 初対面
無料相談の相手は基本的に初対面です。そのため初対面の人に相談するのが苦手、といった方にはデメリットでしょう。